気密測定とn値とc値とは?高気密住宅を実現するための指標について解説
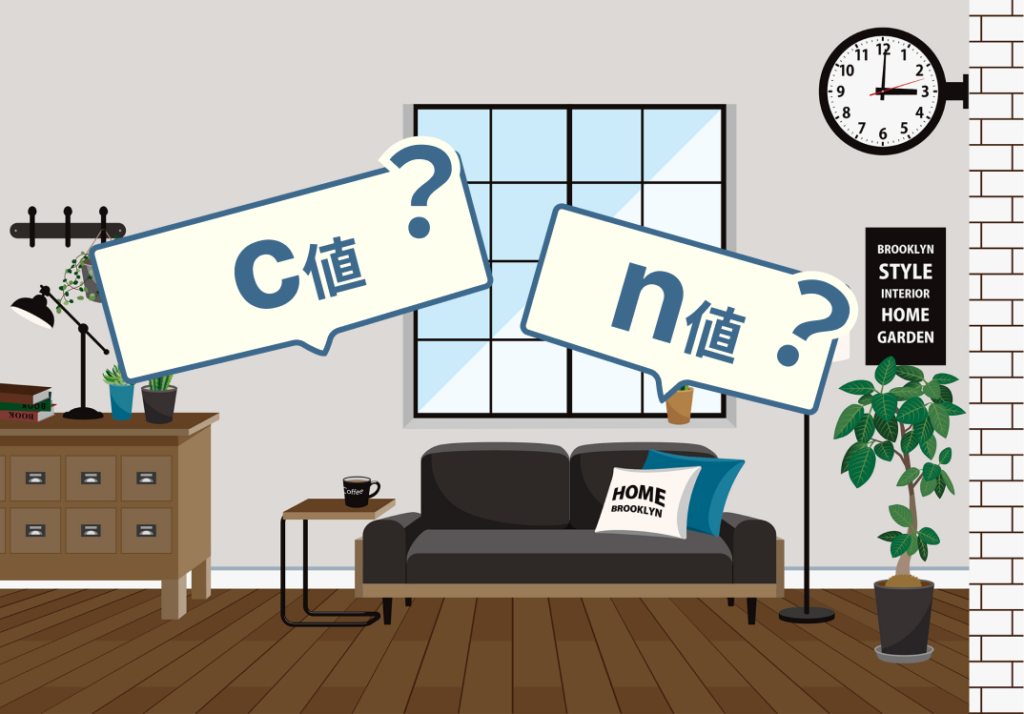
こんにちは!MU設備広報担当です。
家づくりを検討する際、「気密性能」は見落とされがちですが、実は住宅の快適性や省エネ性に大きく影響します。
その中でも、気密測定で得られる「C値」と「n値」は、建物の気密性を示す重要な指標ですが皆さんはどれくらい理解されていますでしょうか。
この記事では、n値の意味や重要性、高気密住宅を実現するためのポイントについて詳しく解説します!
こんな方におすすめの記事です
・省エネ住宅を検討している方:冷暖房の効率を高め、光熱費を抑えたい方に最適です。
・新築・リフォームを予定している方:気密性を確保することで、より快適な住まいを実現できます。
・アレルギーや花粉症に悩んでいる方:隙間を減らすことで、外部からの花粉やホコリの侵入を防げます。
・静かな住環境を求める方:気密性が高いほど、外部の騒音を防ぐ効果があります。
・住宅の長寿命化を考えている方:結露を防ぎ、家の耐久性を高めたい方にもおすすめです。
目次
気密測定とは?
気密測定とは、住宅の隙間の量を数値化し、気密性を評価するための検査です。建物の気密性が高いほど、冷暖房効率が向上し、省エネルギー性能が高まります。また、外部の騒音やホコリ、花粉の侵入を抑える効果もあります。
気密測定では、主に「C値」と「n値」という指標を用います。これらの数値を測定し、住宅の気密性を客観的に評価します。
C値とは?
**C値(相当隙間面積)**とは、建物の床面積1㎡あたりの隙間の合計面積を示す指標です。単位はcm²/m²(平方メートルあたりの平方センチメートル)で表されます。
C値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い住宅とされます。具体的な基準としては、
- 5.0cm²/m²以下 (最低限の気密性)
- 2.0cm²/m²以下(昔の基準値)
- 1.0cm²/m²以下(高気密住宅)
- 0.5cm²/m²以下(超高気密住宅)
気密性が低い住宅では、隙間から暖かい空気が逃げたり、冷気が侵入したりするため、冷暖房の効率が悪くなります。そのため、住宅の断熱性能を最大限に活かすためにも、C値を低くすることが重要です。
n値とは?
n値とは、住宅内の隙間の分布を示す指標で、1〜2の範囲で表されます。
- n値が1に近い:隙間が家全体に均等に分布している
- n値が2に近い:隙間が特定の箇所に集中している
n値が高い(2に近い)場合、特定の場所に大きな隙間が集中していることを意味します。例えば、窓枠や配管周辺などの施工が不十分な箇所に隙間ができやすくなります。一方で、n値が1に近い住宅は、気密性の確保が均等になされており、安定した気密性能を持つことがわかります。

気密測定の数値の見方についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
C値とn値を改善する方法
高気密住宅を実現するには、C値(相当隙間面積)を低減し、n値(隙間特性値)を1に近づけることが重要です。これにより、冷暖房効率が向上し、結露やカビの発生を防ぐことができます。本記事では、C値とn値を改善するための具体的な施工方法を解説します。
1. 開口部の処理を徹底する
開口部は気密性能を大きく左右するため、特に慎重に施工する必要があります。
- 窓やドア周りの気密処理
- 樹脂サッシやトリプルガラス窓などの高気密仕様の建材を選定する。
- 窓枠やドア枠の周囲にはウレタンフォーム、またはコーキング剤を充填する。
- サッシ取り付け後に気密測定を行い、隙間がある場合は補修する。
- 換気ダクト周辺の気密確保
- 換気ダクトの貫通部周囲にはウレタンフォーム、コーキング剤の充填、または気密テープで隙間を塞ぐ。
- 第三種換気や熱交換換気システムの採用時には、適切なダクト施工を行い、空気漏れを防ぐ。
2. 断熱材の施工精度を向上させる
気密性能を高めるためには、断熱材の施工品質を確保することが不可欠です。
- 断熱材の隙間をなくし、密着させる
- グラスウール断熱材は適切な密度で施工し、継ぎ目ができないように注意する。
- 断熱材の継ぎ目には、気密シートやテープを用いて完全に密閉する。
- 吹き込み式断熱材(セルロースファイバー等)の活用
- セルロースファイバーやウレタンフォームなどの吹き込み断熱材を使用すると、隙間が少なく気密性を向上させる。
- 施工時には均一に充填し、特に壁の隅や配管周りの処理を徹底する。
3. 建物の気密測定を実施し、改善点を特定する
気密測定を行うことで、C値の向上を図り、n値を適正な範囲に調整できます。
- 中間測定(工事中)を実施する
- 施工段階で気密測定を行い、施工不良を早期に発見する。
- 測定結果をもとに、気密テープやウレタンフォームで補修を行う。
- 完成後測定で最終確認する
- 竣工後に気密測定を実施し、実際の生活環境のC値とn値を確認する(気密性能の確認)
4. 気密パッキン・気密テープを適切に使用する
配線や配管などの貫通部は、気密性が損なわれやすいため、適切な処理が必要です。
- 貫通部の気密処理
- 電気配線や配管が壁を貫通する部分には、気密パッキンを使用する。
- 気密パッキンを使用できない箇所は、ウレタンフォームやシリコンシーラントで気密を確保する。
- 床と壁の取り合い部分の処理
- 床と壁の接合部には気密テープを貼り、隙間を完全に塞ぐ。
- 壁内部の配管スペースには、気密シートを張り、空気の流出入を防ぐ。
5. 施工管理の徹底と職人の教育
高気密住宅を実現するには、職人のスキル向上と適切な施工管理が重要です。
- 施工マニュアルを作成し、標準化する
- 気密施工に関する詳細なマニュアルを用意し、職人が適切に施工できる環境を整える。
- 施工チェックリストを活用する
- 各工程ごとにチェックリストを作成し、気密処理漏れがないか確認する。
- 施工完了後にチームで確認し、見落としがないか検証する。

高気密住宅のメリット
気密性能を高めることで、以下のようなメリットがあります。
1. 断熱性の向上
気密性が高い家は外気の影響を受けにくいため、室内の温度を安定させやすくなります。
2. 冷暖房効率の向上
隙間が少ないため、冷暖房の効率が良くなり、光熱費の節約につながります。
3. 結露の防止
気密性が低いと、外気と室内の温度差によって結露が発生しやすくなります。結露はカビの原因となり、建物の劣化を招くため、気密性を高めることが重要です。
4. 空気の質の向上
隙間から花粉やPM2.5、害虫などが侵入しにくくなり、室内の空気が清潔に保たれます。
5. 静音性の向上
気密性が高いと、外部の騒音が入りにくくなり、快適な居住空間を作ることができます。
4. まとめ
気密測定によって得られるC値とn値は、高気密住宅を実現するための重要な指標です。
- C値は小さいほど良い → 隙間が少ない住宅
- n値は1に近いほど良い → 隙間が均等に分布している住宅
施工時のポイントを押さえ、気密測定を適切に実施することで、快適で省エネな住まいを実現できます。
気密性能を向上させたい方は、施工実績が豊富な専門業者に相談し、最適な方法を検討しましょう。

